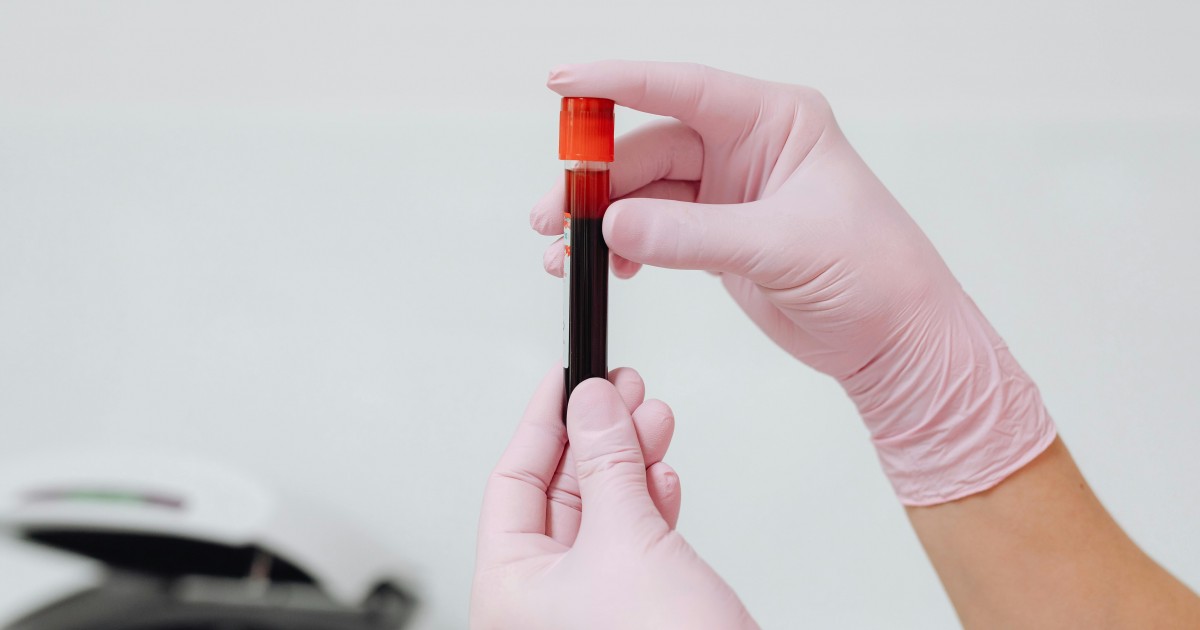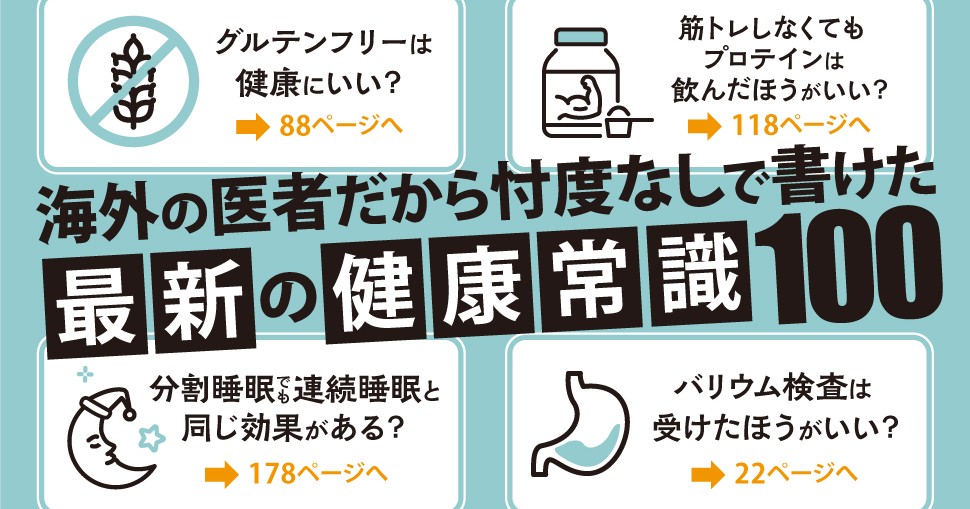医師によって意見が食い違ったら?【医者のいらないラジオ】
ポッドキャスト「医者のいらないラジオ」は、“医者のいらない状態を医者と一緒に目指そう”という矛盾した番組です。先日放送された内容の一部を、レターにて皆さまにお届けします。
現在、NYで医師をしている山田悠史は日々、最先端の論文を読み解き、皆さまにそのエッセンスをお届けすべく活動を続けています。皆さまのサポートのおかげもあり、有益な情報をいち早くお届けできます。ご興味ある方はぜひサポートメンバーとしてお支えいただければ嬉しいです。
医師の経験年数は関係ある?
新里「今日はリスナーさんからの質問に答えていただこうと思います。
ペンネーム・リンリンさんより、医師によって病気の治療方針について言っていることが違っていて困っています。この場合はどうすればいいのでしょうか?とのことです。主治医は若い内科の先生、もう一方の呼吸器内科の先生は総合病院のベテランの専門医のようです。
山田先生、この場合どうすればいいんでしょうか?」
山田「2人の医師から異なる指示を受けた場合、誰でも困惑しますよね。でも困ったらやっぱり、素直にその気持ちを打ち明けて聞くしかないと思うんですよね。こちらの先生にはこう言われたんですけど、どちらがいいのでしょうか?と。
理想的には、異なる医師が違うことを言うことになってしまった場合、その医師同士も直接コミュニケーションを取ることが大事ですよね。
医療はチームで行うもので、そのチームの一員に全ての医師も、患者さんも入っているんですよね。患者さんがいて、そのご家族がいて、主治医も呼吸器内科の医師もいて、そのみんなが一つのチームの一員で、皆が対等な関係であるはずなんですよ。医師の経験年数が高い方がいいとか、若いからダメだとか、そういうこともありません。また、患者さんやそのご家族も大事なチームメンバーなので、何でもかんでも言いなりになる必要もないと思います。
新里「患者さんもしっかりと話し合いに加わるべきということですね。」
山田「医療現場において、全てエビデンスをもとに話ができるってわけではないんですよね。わかっていないことや、グレーなことも多く、選択肢がいくつか出てくることもあるんです。そんな中で、そのグレーゾーンを解決するのは、やはりチーム内のコミュニケーションが大切になるんです。
エビデンスがグレーな場合には、当然それぞれの医師の考え方によって方針に違いが出てくる可能性があります。重視しているものが違ったり、場合によってはその患者さん自身の見え方が医師によって違ったりといったこともあるかもしれません。」
医師と患者は対等な関係
新里「そうなんですね、この場合どのように医師側に伝えるのがいいのでしょうか?」
山田「正直に、困惑していること、2人の医師に違うことを言われたが、どちらが本当なのかわからないことを伝えるのがいいのではないでしょうか。
かかりつけ医の先生がいる場合は、かかりつけ医が指揮者になって情報を統合してほしいなとも思いますが、一方で患者さんからのアクションも大事で、全てのプレーヤーが対等であるべきだと感じます。
医師に対してアクションを起こすっていうのは少し抵抗があるかもしれませんが、何か疑問に思った時にアクションを起こさないと、損してしまうのは患者さん自身なので、そういう意味で何かあれば行動を起こした方がいいと思います。」
新里「同じ病院であればある程度、医師同士でもコミュニケーションは取れているんですか?」
山田「そうですね、何往復ものコミュニケーションがあるかどうかは分かりませんが、文面上のコミュニケーションが少なくともあって、電話上で議論している場合もあると思いますね。
例えば、私が働いているマウントサイナイ大学病院では、例えば呼吸器内科の医師に何か相談をすると必ず主治医にメッセージが返ってきます。もし質問がある場合にはそのままメッセージに質問の返事をしますが、その医師と意見が食い違うことも少なくありません。」
新里「その場合は主治医の先生が指揮をとるのでしょうか?」
医療の情報収集に気をつけよ
山田「そうですね、その場合が多いです。ただ、専門的な病気になると専門医にお任せしますと依頼することもありますし、病気によっても患者さんの状況によっても違いがありますね。
そもそもこちらアメリカの多くの医療機関では、電子カルテの中身が全ての人のアプリで確認でき、患者側、医師側で全く同じ内容が公開されているので、診察を受ければその日のカルテは患者さんも全て見られるようになっています。血液検査の結果も、エックス線の結果も全て見ることが可能なんです。」
新里「そうなんですね、アメリカの医療現場は進んでいますね。
自分自身で2人の医師の考えを比較しようとインターネットや書籍を使って調べ始めると、情報がたくさんあって、非医療従事者には情報の良し悪しを見極めるのが難しいですよね。」
山田「そうですよね。加えて言っておくと、情報収集はぜひ注意していただきたいですね。一時帰国の際に本屋さんに行きましたが、書籍のタイトルや中身にでたらめなものが本当に多く愕然としました。テレビの医療情報も怪しいものも多いので、みなさん気をつけてほしいですし、悩んだら主治医、担当の医師としっかり話してほしいなと思います。」
以下の話題、続きが気になる方はVoicyからぜひお聞きください。
・慢性閉塞性肺疾患(COPD)とは?
・在宅酸素療法とは?
『医者のいらないニュースレター』では、日々のエビデンスに基づく執筆活動をサポートいただける方を募集しています。週 1 本以上のサポートメンバー限定記事も読み放題になりますので、まだの方はこの機会にぜひご検討ください。
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績